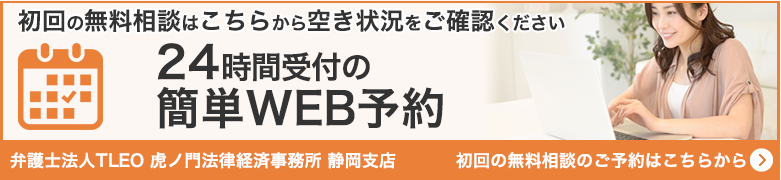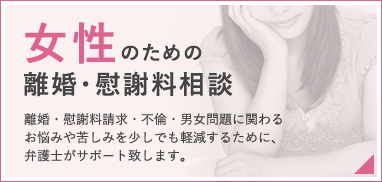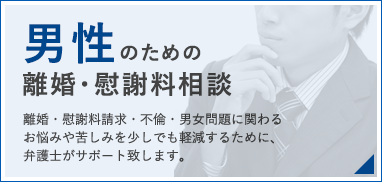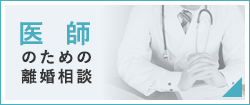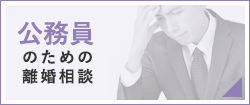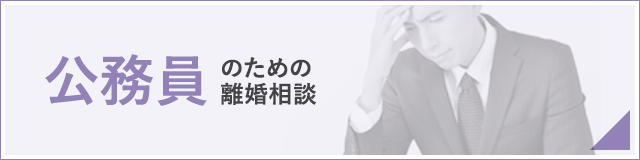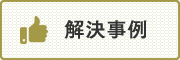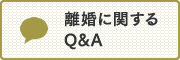医師のための離婚相談
1 悩みの種
 次のようなことでお悩みではありませんか?
次のようなことでお悩みではありませんか?
・医療法人への出資金がある場合,これも財産分与の対象になるのか。
・医師に対する退職金は財産分与の対象になるのか。
・高級腕時計などの動産も財産分与の対象になるのか。
・財産分与の割合は例外なく2分の1になるのか。
・算定表では養育費が算定できないがどうすれば良いのか。
2 医師の離婚相談のポイント
医師の離婚相談は,主に次の5つのことが問題となります。
(1)医療法人への出資金の財産分与
第1に,医療法人への出資金がある場合,その財産分与が問題となります。例えば,夫が医療法人を経営しており,多額の出資金を出している場合があります。このような場合,夫の医療法人に対する持ち分は医療法人の規模や財産によっては極めて高額な資産として評価されることがあります。また,例えば,夫が経営する医療法人に対して,夫のみならず妻も出資をしていた場合,その妻の出資についてどのように処理するかも問題となります。
医療法人の出資金が問題となるときには,必ず弁護士に相談されることをお勧めします。
(2)退職金の財産分与
第2に,退職金の財産分与が問題となることがあります。ご相談者の方の中には,医師には退職金が支給されないと考えていらっしゃる方もいらっしゃいますが,それは誤解です。実際には,勤務医に対しては退職金が支払われることが多いです。また,役員である理事に対しても,節税などの理由から退職金を支給する医療法人もあります。
退職金の額は高額になることが多いですので,退職金が財産分与の対象になるかについて慎重に検討されることをお勧めします。
(3)動産の財産分与
第3に,動産の財産分与が問題となることがあります。この点,一般的には,動産の価値はそれほど高額になることは多くないため,動産の財産分与が問題となることはあまり多くありません。
しかしながら,医師の方の場合には,家具や趣向品が高価な物であることが多く,動産の財産分与についても慎重に検討する必要があります。
(4)財産分与の割合
第4に,財産分与の割合が問題となることがあります。通常,財産分与の割合は2分の1になるのが原則です。これは,夫婦財産は夫婦が協力して築いたものであり,その寄与度は等しいと考えられるからです。しかしながら,このような原則に反して,夫婦の一方の特別な貢献により夫婦財産が増加しているような場合には,財産分与の割合は2分の1にはならないことがあります。
そして,医師の方は,専門的な知識に基づく医療行為の対価として報酬を受け取っており,場合によっては夫婦財産の増加に特別な寄与をしていると評価されることがあります。したがって,医師の方の相談の際には,財産分与の割合についても検討することが必要です。
(5)養育費の算定
第5に,養育費の算定が問題となることがあります。養育費の算定は裁判所が公開する算定表に基づいて算定しますが,所得が高額である場合などはこの算定表に基づいて算定することができません。また,子供が私立学校に通う場合には,そのような学費についてはこの算定表では考慮されていないため,算定表に基づく養育費とは別に交渉により支払いの合意をする必要があります。
このように医師の方の場合には,養育費の算定において様々な問題が生じるため,この点についても慎重な検討が必要です。
3 是非弁護士にご相談ください。
医師の方の離婚相談では,他の職業の方の離婚相談とは異なる特殊性があります。離婚相談をされる際には,そのような特殊性に対して十分な知識がある弁護士に相談されることをお勧めします。また,医師の方は,医師不足の現状もあり,大変お忙しい方が多いです。離婚協議は,場合によっては長期化することもあるため,ご本人で対応することはお勧めできません。可能な限り早い段階で,弁護士に一任されることをお勧めします。
当事務所では,離婚のご相談には全て代表弁護士が自らご相談に応じます。当事務所の初回相談は1時間無料ですので,まずは初回相談にお越しください。必ずお力になります。
離婚相談/性別・年齢・職業別
離婚相談/状況別・お悩み別
-
同居中だが
離婚を検討されている方の
離婚相談 -
別居中だが、不倫・DV等の
離婚原因が無い方の
離婚相談 -
自分が不倫を
してしまった方の
離婚相談 -
相手が不倫をした方
の離婚相談 -
離婚を求められているが
離婚したくない方の
離婚相談 -
離婚自体は争わないが
条件が整わない方の
離婚相談